自分たちはなぜ生まれてきたのか、その答えが森にある。
印象的なセリフだ。
2人の対比
竹野内豊が演じる萱島は、父の死に伴って父の家の売買契約のために田舎の家へ行く。 そこで、山田孝之演じる家の買い手である宇和島と共に事故に遭う。
目が覚めると、そこにいたのは自分たちと一線を画す印象のある女たち。
体は拘束されており、得体のしれない椀に入った汁をふるまわれる。
中には虫が入っていて、飲むのをやめようとしたり、抵抗したりすると、叩かれる。
しかも、彼女たちは一切しゃべらない。
そのことも不気味さ、おそろしさを助長しているようだ。
自分たちとは何かが違う。ここにいてはいけない。
しかし、逃げようとしても、同じところに戻ってきてしまう。
彼女たちの目的すらわからない。
そんななかでも、萱島は少しずつ彼女たちと距離を縮めていくように見える。
一方の、宇和島は露骨にその凶暴性を見せていく。
女性たちを殴る蹴る。萱島はそれをやめさせようとする。
ここで注目したいのは、萱島と宇和島の待遇の差だ。 宇和島はその凶暴性を見せる前から、すでに萱島と待遇の差があった。
捕えられた際に、宇和島は物置のようなところで縛られていたのに対し、萱島は布団に寝かされていたのだ。
これには意味がある。 彼女たちは、誰が自分たちの敵なのかを把握していたためだ。
そう。彼女たちは、森に生きる生き物たち。
自然を壊して、廃棄物処理場を建設しようとしていた宇和島は、彼女たちにとって間違いなく敵だった。
一方、萱島は森にあった父の家を宇和島に売ろうとしていたものの、事情をよく知らなかった。
萱島の父は、生前から森を守ろうとしていたため、萱島は彼女たちにとってまだ味方ではないものの、味方にできる存在だと思ったのではないだろうか。
あるいは、彼に森の未来を託そうとしたのかもしれない。
概念としての女
森の生き物たちが、すべて女性で描かれた意味はなんだったのか。
生き物は、オスもメスもいるのだし、別に男性でもよかったはずだ。
それがなぜ、男性ではなく女性だったのか。
これは、おそらく女性が子を産む存在だからだろう。
未来へいのちをつなぐ象徴的な存在としての「女性」だったのではないだろうか。
さらにいえば、森は地球の象徴とも考えられる。
描かれているのは、異世界のような「森」ではあるのだが、その実この作品はもっとスケールの大きなことを言っていて、地球の未来の話をしているとも取れる。
人間が便利さを求めていくうちに、破壊されていく自然。
欲望のままに行動する宇和島は、欲望のままに環境を破壊する「人間」を体現しているともいえる。
森=地球。そう考えると、萱島が最後、異世界に戻り死んでしまったのも地球と人間は運命共同体だという示唆なのかもしれない。ラストシーンで、萱島の彼女が、森にある萱島の父の家を取り戻し、新たないのちをつないで子どもを生んで育てていることがわかる。
このことは、これからの人間の行動次第で、森(自然)と人間が共存できる明るい未来もあるのだということなのかもしれない。
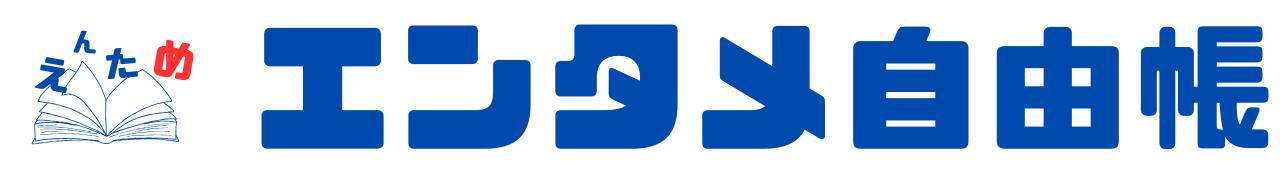



コメント